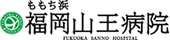治療のながれ
不妊症の原因はさまざまです。女性、男性、または両方に原因がある場合があります。不妊症の治療は、一般検査で原因を探りながら、タイミング法などの治療を並行して開始します。一般検査の結果によっては、腹腔鏡検査や子宮鏡検査などの特殊検査に進みます。
晩婚化によって、治療を受けられる方の高齢化が進んでいますが、30代後半や40歳以上になると卵子数が減少して、卵子の質も低下します。
また染色体異常の卵子も増加するため、妊娠しにくくなるうえ、流産の可能性も高まりますので、妊娠しやすい時期に、より妊娠率の高い治療にステップアップすることをおすすめしています。
卵巣内の卵子の数(在庫)の指標となるAMH(アンチミューラリアンホルモン)の検査を行い、AMHの値と不妊原因、年齢をもとに治療回数を患者様と相談して決めます。
治療のステップ
Ⅰタイミング法
タイミング法とは、「最も妊娠しやすいタイミングにあわせて性交渉を行う」方法です。
スクリーニング検査の結果をもとに排卵日を予測し、効果的な性交渉のタイミングを医師がアドバイスします。タイミング法を6か月続けても妊娠しない場合は、次のステップに進みます。
Ⅱ薬物治療
ホルモン環境を整える薬物治療
排卵障害や黄体機能不全、高プロラクチン血症など、検査結果により必要な薬物治療を行います。
Ⅲ人工授精(AIH)
人工授精とは、一般不妊症治療の一つで、「精子を人工的に子宮腔内に注入する」方法です。
排卵日に合わせて排卵直前から排卵直後の時期に行います。性交後検査(フーナーテスト)の結果が良くない場合やタイミング療法の次のステップで行う治療です。
人工授精を4~6周期行っても妊娠しない場合や女性の年齢が高い場合は、体外受精(IVF)や顕微授精(ICSI)を行います。
基本的な治療の流れ
(1)人工授精を行う日時を決定する
排卵日または排卵前日に合わせて、人工授精を行う日時を決めます。
(2)採精
自宅または当センターで採精します。当センター内で採精する場合は、予約が必要です。
当センター受付にお申し出ください。
当センターでは、精子の状態をより良くするため、また子宮収縮やそれに伴う疼痛防止のためにすべて良好精子洗浄濃縮法(P-AIH)で人工授精を行います。精子の洗浄・濃縮に約1時間程度かかります。
(3)人工授精(精子を子宮腔内に注入)
柔らかいチューブを使って、精子を子宮腔内に注入します。治療後は、しばらくの間、内診台上で安静にします。
感染防止のため2日間は抗生剤を服用します。
(4)妊娠判定
人工授精後、12~14日目に妊娠反応検査を行います。
- 対象
-
- 精子の数が少ない(乏精子症)、精子の運動性が低い(精子無力症)などの原因がある場合
- 精子-頸管粘液不適合で性交後検査(フーナーテスト)を繰り返しても精子の数や動きが良くない場合
- 頸管粘液減少症でホルモン治療を行っても改善しない場合
- 性交障害がある場合(セックスレスを含む)
- 原因不明の不妊症でタイミング法を半年以上行っても妊娠しない場合など
Ⅳ高度生殖補助医療(ART)
Ⅳ-A体外受精(IVF)
体外受精・胚移植(IVF-ET)は、「精子と卵子を採取し、体外で受精させて受精卵を子宮に戻す」方法です。
基本的な治療の流れ
(1)排卵誘発(排卵誘発剤を投与して卵胞を育てる)
状態の良い卵子を子宮に戻して妊娠する可能性を高めるためには、できるだけ多くの卵子を採取する必要があります。
このため正常な排卵がある人でも排卵誘発剤(FSH、HMG製剤)を注射します。妊娠の確率を上げるために必要な最初のステップです。
排卵誘発剤(FSH、HMG製剤)の注射は、月経開始3日目頃から通常7~14日間、毎日行います。
(注射の量、回数は個人差があります)
注射開始後6~8日目から、経腟超音波で卵子の発育状態を2~4日毎に検査します。
卵子が十分に成長したら、卵子の成熟を促すHCG(胎盤性性腺刺激ホルモン)を注射します。
このHCG注射は、採卵時間の都合上、採卵日の前々日の午後11時以降に行う必要があります。
- 排卵誘発
排卵を誘発するには、いくつかの種類があります。卵巣の状態や治療経過によって決定します。
ショート法:採卵周期の月経1日目からGnRHアゴニスト(点鼻薬:ナサニール等)を使用し、排卵時期をコントロールしやすくします。月経3日目頃から注射で排卵誘発を開始します。
ロング法:採卵周期の前の周期の高温相からGnRHアゴニスト(点鼻薬:ナサニール等)を使用します。
月経3日目頃から注射で排卵誘発を開始します。アンタゴニスト:排卵誘発剤によって十分に育ってきた卵胞の早期排卵を抑制します。卵胞経がある程度(約14mm)成長したところでGnRHアンタゴニストを使用します。
低刺激法:自然周期で経過を見ながら、作用の穏やかな飲み薬や注射で卵胞を育てます。
- HCG注射
HCGは黄体化ホルモン(LH)と同様の作用を持つ薬剤で、成熟した卵胞に作用して排卵を促します。
注射または、状況によってはスプレーを使用します。投与後おおよそ34?36時間後に排卵が起こります。
(2)採精
卵子を採取する日の午前中に精液を採取(採精)します。採精の日程は、卵子の成長の程度によって決まりますので、2日前にしか分かりません。
自宅または当センターで採精します。当センター以外で採精する場合は、採取後1~2時間以内に病院にお持ちください。
当センター内で採精する場合は、予約が必要です。当センター受付にお申し出ください。
(3)採卵
HCG注射の33~36時間後(翌々日の午前9~11時)に卵子を採取(採卵)します。
採卵の順番によって来院時間が異なります。
経腟超音波を確認しながら、卵巣に針を刺して卵子を採取します。麻酔を使用するため採卵中の痛みはありません。
採卵日は月経の開始日、卵子の発育状態によって決定しますので2~3日前にしか分かりません。このため、治療前に採卵日を指定することはできません。ただし、前周期にピルを使ったり、点鼻薬(ナサニール)を月経7日前から使ったりすること(ロング法)で、ある程度の調整は可能です。
採卵日は、お腹の中で出血が起こる可能性があるため2時間程度、休憩が必要です。
麻酔を使用して採卵しますので、ご自身の運転によるお車での来院はお控えください。
(4)受精・培養
採卵当日に卵子と精子を体外で受精させます。
受精卵は、移植に適した状態になるまで1~5日間(通常2~3日間)培養します。
体外受精を2回実施しても受精しない場合は、精子の受精能力に問題がある可能性が考えられますので、顕微授精を考慮します。
(5-1)子宮内への胚移植
受精卵(胚)を子宮に戻します。
柔らかいチューブを使って、受精卵を腟から子宮内に戻します。
胚移植は通常、採卵後2~3日目の午後に行いますが、受精卵の数、状態によっては採卵後5日目(胚盤胞移植)に移植する場合もあります。
(5-2)胚の凍結保存
一度、採卵を行うと複数個の卵子が得られます。このうち受精した良好な胚を移植しますが、余った胚を余剰胚として凍結保存しておくことができます。妊娠が成立しなかった場合でも、別の周期に胚を融解して再度移植することが可能です。この方法によって、排卵誘発や採卵に伴う身体的・経済的負担を軽減できます。
(凍結費用・保管費用などが必要です)
(6)胚移植後のホルモン補充
子宮内の環境を良くして妊娠しやすいように胚移植後約10日間にわたって女性ホルモンの補充を行います。
方法:
・黄体ホルモン連日内服
・黄体ホルモン腟錠連日投与
・黄体ホルモン連日注射
・HCG隔日注射 など
一人ひとりにあった方法を選択します。
(7)妊娠判定
胚移植後12~14日目に尿検査で妊娠しているかどうかを確認します。
- 対象
-
- 卵管が閉塞している場合
- 卵管周囲に癒着があり受精卵の子宮への移動に障害がある場合(卵管因子不妊)
- 精子の数が少ない(乏精子症)、精子の運動性が低い(精子無力症)などの原因がある場合(男性因子不妊)
- 子宮内膜症
- 免疫性不妊症
- 原因不明の不妊症 など
- 最低3回、可能であれば6回は治療を行うことをおすすめします。希望があれば何回でも治療を行いますが、7回目以降は、妊娠する可能性が非常に低くなることを予めご了承ください。
Ⅳ-B顕微授精(ICSI)
顕微授精(ICSI)も、「体外で得られた受精卵を子宮に戻す」という点では体外受精と同じです。
精子と卵子を培養液に入れて自然に受精するのを待つ体外受精に対して、顕微授精は、「顕微鏡と細い針状のガラス管を用いて卵子と精子を人工的に授精させる方法」です。
人工授精は治療自体が1日程度で終わるのに対して、体外受精・顕微授精は排卵を促す注射を打ったり、採卵日の調整をしたりするために数日間通院する必要があります。
何らかの受精障害があり、培養液の中で自然に受精するのが難しい場合は、顕微授精を行うことになります。
基本的な治療の流れ
(1)排卵誘発(排卵誘発剤を投与して卵胞を育てる)
状態の良い卵子を子宮に戻して妊娠する可能性を高めるためには、できるだけ多くの卵子を採取する必要があります。
このため正常な排卵がある人でも排卵誘発剤(FSH、HMG製剤)を注射します。
妊娠の確率を上げるために必要な最初のステップです。
排卵誘発剤(FSH、HMG製剤)の注射は、月経開始3日目頃から通常7~14日間、毎日行います。
(注射の量、回数は個人差があります)
注射開始後6~8日目から、経腟超音波で卵子の発育状態を2~4日毎に検査します。
卵子が十分に成長したら、卵子の成熟を促すHCG(胎盤性性腺刺激ホルモン)を注射します。
このHCG注射は、採卵時間の都合上、採卵日の前々日の午後11時以降に行う必要があります。
- 排卵誘発
排卵を誘発するには、いくつかの種類があります。卵巣の状態や治療経過によって決定します。
ショート法:採卵周期の月経1日目からGnRHアゴニスト(点鼻薬:ナサニール等)を使用し、排卵時期をコントロールしやすくします。月経3日目頃から注射で排卵誘発を開始します。
ロング法:採卵周期の前の周期の高温相からGnRHアゴニスト(点鼻薬:ナサニール等)を使用します。
月経3日目頃から注射で排卵誘発を開始します。アンタゴニスト:排卵誘発剤によって十分に育ってきた卵胞の早期排卵を抑制します。
卵胞経がある程度(約14mm)成長したところでGnRHアンタゴニストを使用します。低刺激法:自然周期で経過を見ながら、作用の穏やかな飲み薬や注射で卵胞を育てます。
- HCG注射
HCGは黄体化ホルモン(LH)と同様の作用を持つ薬剤で、成熟した卵胞に作用して排卵を促します。
注射または、状況によってはスプレーを使用します。投与後おおよそ34?36時間後に排卵が起こります。
(2)採精
卵子を採取する日の午前中に精液を採取(採精)します。採精の日程は、卵子の成長の程度によって決まりますので、2日前にしか分かりません。
自宅または当センターで採精します。当センター以外で採精する場合は、採取後1~2時間以内に病院にお持ちください。当センター内で採精する場合は、予約が必要です。当センター受付にお申し出ください。
(3)採卵
HCG注射の33~36時間後(翌々日の午前9~11時)に卵子を採取(採卵)します。
採卵の順番によって来院時間が異なります。
経腟超音波を確認しながら、卵巣に針を刺して卵子を採取します。麻酔を使用するため採卵中の痛みはありません。
採卵日は月経の開始日、卵子の発育状態によって決定しますので2~3日前にしか分かりません。
このため、治療前に採卵日を指定することはできません。ただし、前周期にピルを使ったり、点鼻薬(ナサニール)を月経7日前から使ったりすること(ロング法)で、ある程度の調整は可能です。
採卵日は、お腹の中で出血が起こる可能性があるため2時間程度、休憩が必要です。
麻酔を使用して採卵しますので、ご自身の運転によるお車での来院はお控えください。
(4)受精
採卵後、培養した卵子を顕微鏡下で、細いガラス管を用いて運動性の良い精子を卵子に注入し受精させます。
(5)受精の確認&培養
採卵の次の日に受精しているかを確認します。受精した卵は、分割卵へと発育します。
さらに培養をすすめ胚盤胞(桑実胚)へと育てることもあります。
※インキュベーターと呼ばれる温度とガス濃度をコントロールし、体内と似た環境を作ることができる機械で培養します。
(6-1)子宮内への胚移植(ET)
採卵から2~3日目に、培養した分割卵(4細胞期胚、8細胞期胚)を細い管で子宮内に戻します。
これを胚移植といいます。
受精卵の数、状態によっては、採卵後5~6日目に胚盤胞で移植する場合もあります。
(6-2)胚の凍結保存
一度、採卵を行うと複数個の卵子が得られます。
このうち受精した良好な胚を移植しますが、余った胚を余剰胚として凍結保存しておくことができます。
妊娠が成立しなかった場合でも、別の周期に胚を融解して再度移植することが可能です。
この方法によって、排卵誘発や採卵に伴う身体的・経済的負担を軽減できます。(凍結費用・保管費用などが必要です)
(7)妊娠判定
胚移植後12~14日目に尿検査で妊娠しているかどうかを確認します。
- 対象
-
- 重症の男性不妊の場合
- 受精障害がある場合(体外受精では受精しない)
- ※他院で治療を受けられていた方は、途中のステップから始めます。
- ※卵管因子・抗精子抗体(陽性例)や男性因子のケースでは、流れが異なります。
ARTに追加して行う治療法
保険診療
先進医療(保険診療と併用可能)
自由診療(保険診療と併用不可能)
保険診療
人為的卵子活性処理
高濃度のカルシウムイオン濃度が含まれている培養液に卵子を浸けることで、卵子内部のカルシウムイオン濃度を上昇させ、受精の手助けをします。
※顕微授精をしても受精卵を得られなかった、受精成績が不良だった方におすすめします。
AHA(アシステッド・ハッチング)
胚が着床できるよう透明帯から脱出するのを補助するための方法です。
ガラスのピペットや赤外線レーザー照射によって、細胞を傷つけないように透明帯の一部を薄くしたり、穴を開けたりします。
胚は透明帯という殻から脱出しないと着床することはありません。脱出できないという可能性を防ぎます。
※凍結融解胚移植では一部必要性のない方を除き、全症例で使用します
高濃度ヒアルロン酸含有培養液表
移植時に使用するヒアルロン酸がたくさん入った培養液です。
着床するためには胚と子宮内膜が接着する必要性があります。その接着剤となるのがヒアルロン酸です。この培養液には非常にたくさんのヒアルロン酸が含まれているため、胚と子宮内膜を接着しやすくしてくれます。
※胚移植では全症例で使用します
先進医療(保険診療と併用可能)
タイムラプスインキュベーター(タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養)
受精卵を培養庫から出さずに経時的に観察できる機械で、受精後の卵の成長過程の多くの情報を得ることができます。
従来の胚培養はインキュベーターという培養庫から胚を取り出して観察する必要があり、胚にストレスを与えていました。しかし、タイムラプスインキュベーターにはカメラが搭載されており、胚をインキュベーターから取り出すことなく、モニター上で観察することができます。胚へのストレスが軽減され、一定間隔で撮影した画像を繋いで動画として観察することができ、従来に比べてより多くの胚の情報が得られ、移植時に良好な胚の選択などを行うことが可能になりました。
※タイムラプスインキュベーターは卵子と精子を一緒にしてから使用します
※体外受精・顕微授精では全症例で使用します
臨床成績
当院でもタイムラプスインキュベーターを導入してから、胚の培養成績および妊娠率が大きく向上しています。
※卵子の質、精子の質によっては臨床成績の向上が得られない可能性もあります
デメリット
直接人体に影響を及ぼすものではないため副作用などのデメリットはありません。
費用
タイムラプスインキュベーターは先進医療として申請を行うため、費用は全額自己負担となります。
※費用の補助金制度については、各自治体にお問い合わせください。
ZyMot(膜構造を用いた生理学的精子選択術)
化学物質や遠心分離機を使用せずに形態良好な運動精子を回収できる装置です。
従来の化学物質や遠心分離機を使用した方法では形態不良精子や非運動精子も回収してしまいます。また、精子DNAを損傷してしまう可能性もあります。精子DNAの損傷は治療成績にも影響を及ぼします。ZyMotスパムセパレーターでは精子DNAの損傷を抑制することができます。
精子のDNA損傷を防ぎ、形態良好な運動精子を回収することができるとされています。
※顕微授精では全症例で使用します。ただし、精液所見次第では使用できないことがあります
方法
精液注入口より精液を注入し、精子の自身の前進運動でメンブレンを通過し精液回収口に集まります。精液回収口に集まった形態良好な運動精子を回収します。

メリット
形態良好で運動性の高い精子を回収でき、メンブレンにより奇形精子や精液中の不純物の回収を減らせます。また、精子DNAの損傷を抑制することができます。
良好な精子を使用していくことで、治療成績(胚盤胞到達率、臨床妊娠率、流産率など)の改善の可能性があります。
※精子の質、卵子の質によっては必ずしも治療成績の改善が得られない可能性もあります
デメリット
原精液中の精子が少ない、運動性が低いなどの精子の状態によっては使用できないことがあります。ZyMotでは化学物質や遠心分離機を使用方法と比べ、回収できる精子数が減る傾向にあるため体外受精を検討するときには使用できない可能性があります。
費用
膜構造を用いた生理学的精子選択術(ZyMotスパムセパレーター)は、先進医療として行うため、費用は全額自己負担となります。
※費用の補助金制度については、各自治体にお問い合わせください。
PICSI(ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術)
成熟精子のヒアルロン酸結合能を利用した顕微授精をする際の精子選択術です。DNA損傷の少ない成熟精子はヒアルロン酸に結合することができます。
この特徴を利用し顕微授精(ICSI)を行うときに通常の方法に比べ、より厳格に精子を選別することができる方法です。この選別方法は、体内で受精するときに自然に行われている選別に近い形で精子を選別することができます。
DNA損傷の少ない成熟精子を治療に用いることは治療成績にも影響します。
※顕微授精をされる方は使用をおすすめします
方法
ヒアルロン酸が入った培養液の中に精子調整後の精子を入れます。数分後にDNA損傷の少ない成熟精子はヒアルロン酸に結合し、運動が非常に緩慢もしくは動かなくなります。この反応を示した精子を顕微授精に用います。

メリット
DNA損傷の少ない成熟精子を選別することができ、治療成績(受精率、胚盤胞到達率、臨床妊娠率、流産率など)の改善の可能性があります。
※精子の質、卵子の質によっては必ずしも治療成績の改善が得られない可能性もあります
デメリット
精子の数が少ない、運動性がかなり低いなど、精子の状態によっては使用できないことがあります。その場合は、通常の顕微授精を行います。
費用
PICSI(ヒアルロン酸結合能を用いた生理学的精子選択術)は先進医療として行うため、費用は全額自己負担となります。
※費用の補助金制度については、各自治体にお問い合わせください。
SEET法(子宮内膜刺激術)
胚盤胞を移植する2~3日前に受精卵を培養した培養液を子宮内に移植する方法です。
自然妊娠では受精卵と子宮のシグナル伝達をすることで、着床しやすい環境を整えると考えられています。通常の体外受精―移植では、このシグナル伝達が不足している可能性があります。そこで胚盤胞まで培養した培養液を移植2~3日前に子宮内に注入し、シグナル伝達を行うことで着床しやすい環境を整えて、妊娠率の改善を図る方法です。
方法
採卵した周期に胚盤胞まで培養した培養液と胚盤胞を凍結します。移植する周期の移植2~3日前に凍結しておいた培養液を融解し、子宮内に注入します。後日、胚盤胞を移植します。 ※培養液の凍結保存期間は凍結日より原則1年間とします

メリット
受精卵と子宮のシグナル伝達が行われることで着床するための環境を整えます。妊娠率が向上する可能性があります。
※移植胚の質、内膜の状態によっては必ずしも妊娠率の向上が得られない可能性もあります。
デメリット
培養液を移植することで、低確率ですが子宮内感染症のリスクがあります。
費用
SEET法 (子宮内膜刺激胚移植法)は、先進医療として行うため、費用は全額自己負担となります。
※費用の補助金制度については、各自治体にお問い合わせください。
二段階胚移植術
自然妊娠では、受精卵と子宮のシグナル伝達をすることで、着床しやすい環境を整えると考えられています。通常の体外受精―移植では、このシグナル伝達が不足している可能性があります。そこで初期胚を移植2~3日前に子宮内に移植し、初期胚にシグナル伝達を行ってもらい、着床しやすい環境を整えることで妊娠率の改善が期待される方法です。
※SEET法と違い、2個移植となります
方法
胚盤胞移植の2~3日前に初期胚を移植します。初期胚移植の2~3日後に胚盤胞を移植します。

メリット
受精卵と子宮のシグナル伝達が行われることで、着床するための環境が整い、妊娠率が向上する可能性があります。
※移植胚の質、内膜の状態によっては必ずしも妊娠率の向上が得られない可能性もあります
デメリット
初期胚を1個、胚盤胞を1個の計2個を移植するため、多胎妊娠の可能性があります。
2度の移植をすることで、低確率ですが子宮内感染症のリスクがあります。
費用
二段階胚移植術は先進医療として行うため、費用は全額自己負担となります。
※費用の補助金制度については、各自治体にお問い合わせください。
EndomeTRIO検査
子宮内膜は、胚が着床し赤ちゃんが成長していく場所です。EndomeTRIO検査は、体外受精や顕微授精で健康な胚を移植しても妊娠しない場合などに、着床のタイミングを調べる検査(ERA)と、子宮内膜の環境を調べる検査(EMMA・ALICE)をまとめて行う検査です。着床できない(着床不全)原因を調べることができるとされています。
※ERA検査のみ、EMMA検査とALICE検査のみでも検査が可能です
それぞれの検査
- ERA(子宮内膜着床能検査):着床率が最も高まるタイミングを調べるための検査です。検査結果を基に、移植の時期をずらしたり、黄体ホルモンの開始日をずらしたりして、最適な時期に胚移植を行います。
- EMMA(子宮内膜マイクロバイオーム検査):子宮内膜の細菌の割合を調べる検査です。子宮内膜の健康な菌のレベルが低い場合は、妊娠の確率が低くなる可能性があります。細菌のバランスが悪い場合は、抗生剤を処方します。
- ALICE(感染性慢性子宮内膜炎検査):慢性子宮内膜炎を起こしているかを調べる検査です。 子宮内膜炎は、着床障害を引き起こす可能性があります。原因菌が検出された場合は、内膜炎の原因となっている細菌を特定し、複数のお薬の中から適切な抗生剤で治療します。
費用
EndomeTRIO検査は先進医療として申請を行うため、費用は全額自己負担となります。
※費用の補助金制度については、各自治体にお問い合わせください。
内膜スクラッチ法
胚移植をする前に人工的に子宮内膜を引っ掻き、小さな傷をつける方法です。傷ついた子宮内膜を修復するために、さまざまな成長因子などが分泌され、着床しやすくなるとされています。 Amihai Barashらの研究で子宮内膜をサンプリングした後に体外受精で胚移植を行った場合、通常より妊娠率が増加したと報告され注目されました。
適応
複数回、胚移植したにもかかわらず妊娠に至らない方を対象としています。
方法
移植をする前の月経周期の黄体期に子宮内膜細胞診用の器具を使用して、子宮内膜を引っ掻き、小さな傷をつけます。
翌周期に通常通りのスケジュールで胚移植を行います。
メリット
内膜の刺激と修復により着床率が高くなる可能性があります。
デメリット
ごく低確率ですが子宮内感染症のリスクがあります。
費用
内膜スクラッチ法は先進医療として行うため、費用は全額自己負担となります。
それ以外の胚移植などの診察・検査・薬剤等は保険診療となります。
※費用の補助金制度については、各自治体にお問い合わせください。
自由診療(保険診療と併用不可能)
着床前診断(PGT-A:着床前胚染色体異数性検査)
受精卵(胚)の一部を採取し、採取した細胞から染色体異常を調べる検査です。流産しにくい着床しやすい胚を検査します。
※高齢、着床しない(着床不全)、流産を繰り返す(反復流産)などで治療がうまくいかない方におすすめします
※判定不能となった受精卵(胚)は、その個数につきご返金します
PFC-FD療法(自己血小板由来成分濃縮物療法)
ご自身の血液を約50ml採血し、再生医療センターにて多血小板血漿由来の成長因子を抽出します。フリーズドライの状態で約3週間後に当院に返送されます。半年間の保存が可能です。
(1)子宮内への注入
胚移植の数日前に子宮内に注入することで、内膜を厚くしたり、炎症を抑えたりするなど子宮内の環境の改善が期待されます。
(2)卵巣内に注入
未だ発展途上ですが、投与2周期目以降のAMHの上昇などが報告されています。
※これらの方法は、卵巣の状態、卵子の質、精子の質などによっては必ずしも治療成績の改善が得られるわけではありません
受付時間
| 受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前中(9:00~11:00) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
初診の方
092-832-1226(予約専用)
※電話受付時間/9:00~17:00(月~土曜 ※祝日除く)
※お電話で、「リプロダクションセンターの初診の予約です」とお伝えください。
※初診の方は、婦人科をご受診いただきます。
再診の方
092-832-1226(予約専用)
※電話受付時間/13:00~17:00(月~土曜 ※祝日除く)
※お電話で、「リプロダクションセンターの予約です」とお伝えください。
※2回目以降のご受診は、当センターをご受診いただきます。
所在地
〒814-0001
福岡市早良区百道浜3丁目6番45号